|
|
 |
 |
メディア掲載
三大技法に学ぶ
日本伝大東流合気柔術
三 天之巻 [合
気之術編]
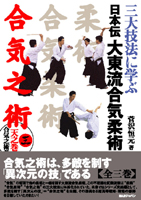 菅沢師範の
3部作、その完結編である天之巻 「合気之術編」が7月下旬に発売される。 菅沢師範の
3部作、その完結編である天之巻 「合気之術編」が7月下旬に発売される。
合気之術は、多敵を倒す「異次元の技」である。完結編である本書では、多敵を制す「異次元の技」=合気之術を公開する。その高等戦略・戦術の修得を目指し
ていただきたい。
二 人之巻 [合気柔
術編]
 3部作、「三大技法
に学ぶ 日本伝大東流合気柔術」の第2弾となる「人之巻 [合気柔術編]」が、4月末から書店で入手可能となっている。 3部作、「三大技法
に学ぶ 日本伝大東流合気柔術」の第2弾となる「人之巻 [合気柔術編]」が、4月末から書店で入手可能となっている。
人之巻では、無数に展開する「裏の技」=合気柔術を公開する。大東流の真髄”合気”を、是非身につけて欲しい。
一 地之巻 [柔
術編]
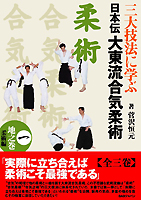 平成18年1月21
日、株式会社BABジャパンより菅沢師範の著
作、 平成18年1月21
日、株式会社BABジャパンより菅沢師範の著
作、
「三大技法に学ぶ 日本伝大東流合気柔術 一 地之巻 [柔術編]」
が発売された。
大東流合気柔術を、柔術、合気柔術、合気之術とする日本伝(大東流三大技法)合気柔術で世に示した、故鶴山晃瑞師範。本作では三大技法のうち、柔術に焦点
を当て真伝を公開している。
「実際に立ち合えば柔術こそ最強である」。裂帛の気合、多重のきめを含むその極意に各目して欲しい。
日本伝三大技法と合気の階梯 (月刊秘伝
連載終了)
「平成18年8月号」(7月14日発売)
特別編 菅沢恒元師 自らの師を語る −我が合気の源流、そして武の道統
「合気の階梯」が7月号にて終結を迎えた。菅沢師範の想いは、師より自分の中に伝え遺された”合気の階梯”を書として遺したい、という事にあったという。
今回は連載の総決算として、菅沢師範にとっての師にあたる鶴山晃瑞師範、そして柳生新陰流の大坪指方師範の武術、人物像を繙き、今を偽らしめている”武の
道統”を探ってみたい。
「平成18年7月号」(6月14日発売)
最終回 三大技法とは? −日本伝における三層構造の意味
最終回では、総まとめとして、日本伝が持つ最大の特徴と言える”三層構造”にスポットを当て、この精緻に構築された至高の武術を再認識してみる。
「平成18年6月号」(5月13日発売)
第41回 多敵の構え その11 −八方分身と空間認識
今回は、いよいよ大東流最奥義の一つ「八方分身」を解析する。全周囲からの攻撃に対応するために必要なものは、もはや”技術”のレベルではない。
極めて感覚的な極意、それは”空間認識”である。
「平成18年5月号」(4月14日発売)
第40回 多敵の構え その10 −接点の移行と連鎖制御
今回は、合気における接触点を移行させる技法を中心に紹介する。複数敵を一人で制するには、合気ならではの方法論が存在する。それが「連鎖制御」である。
「平成18年4月号」(3月14日発売)
第39回 多敵の構え その9 −同時攻撃への対処
今回は、複数の敵が同時に攻撃を仕掛けてきた際の技法群を中心に紹介する。多敵戦ならではの、この上ない緊急事態。これを打破する、合気之術に秘められた
戦
略とは...
「平成18年3月号」(2月14日発売)
第38回 多敵の構え その8 −4次元体技法への展開
今回は、4次元体への必須技法ともいえる「不動金縛り」を主軸に論を進める。空間を時間軸的に制御するには、まず相手を止める事。そして”盾”とする事に
よって制御範囲を拡大させていく。
「平成18年2月号」(1月14日発売)
第37回 多敵の構え その7 −3次元体立法の修得
今回は小手返し〜”逆小手”を中心に展開される技法郡を紹介する。攻撃してきた手でなく逆側を取る”逆小手”は、強烈な陽動策であると同時に、「全方位
性」獲得のための重要な手がかりとなる。
「平成18年1月号」(12月14日発売)
第36回 多敵の構え その6 −3次元体立法の修得
前回に引き続き、一歩出て、引き、再び戻る、だけという簡便な運足を中心とした技法群を紹介する。
さらに”当て”の要素を加え、より実戦的に展開される「合気之術」は多敵戦における極意を示す。
「平成17年12月号」(11月14日発売)
第35回 多敵の構え その5 −3次元体立法の修得
今回は前回紹介した「合気呼吸体操」の内の”小手返し”の運足を中心とした技法群を紹介する。一歩出て、引き、再び出る、だけという簡便な身捌きだけに、
絶大な実戦性を持つ。
「平成17年11月号」(10月14日発売)
第34回 多敵の構え その4 −3次元体立法の修得
今回は背後から両手首を掴まれるケースを中心とした技法群。急を要す場面ゆえ、瞬時に捌かねばならない。それを可能とするのが”合気”であり、「合気之
術」が”天之巻”たるゆえんだ。
「平成17年10月号」(9月14日発売)
第33回 他敵の備え その3 −三次元体立法の修得
今回からは立法に入る。前回までの座法により養われた体捌きはより大きく、速く、能動的な技法へと発展する。それは、日本伝大東流の奥義「八方分身」への
道でもある。
「平成17年9月号」(8月14日発売)
第32回 他敵の備え その2 −三次元体半座法の修得
三大技法の最高位「合気の術」編。上級武士が戦略論として学ぶために編まれた体系には、実戦武術の最終目的”多的の位”へ対応するための術理が秘められて
いる。
「平成17年8月号」(7月14日発売)
第31回 他敵の備え その1 −三次元体半座法の修得
いよいよ三大技法の最高位「合気之術」編に入る。
上級武士が戦略論として学ぶために編まれた体系には、実戦武術の最終目的”多敵之位”へ対応するための術理が秘められている。
「平成17年7月号」(6月14日発売)
第30回 懐剣之事その2 −対懐剣、対太刀における技法
前回に引き続き、懐剣術の技法群を紹介する。その精妙にして緻密な理合、独特な技法には、武器を手にせぬ現代にあって見失いがちな、極めて実践的な意味が
隠されている。
「平成17年6月号」(5月14日発売)
第29回 懐剣之事 −懐剣対懐剣における技法
今回より紹介する懐剣術は、これまでの”合気杖”を初伝とした、さらに高度な技法群である。
元々は女子のためのものでありつつも、独特、精妙にして緻密な理合。ここには武術としての本質が垣間見えている。
「平成17年5月号」(4月14日発売)
第28回 対武器の技法 −合気杖における徒手技法「合気投げ」
対武器の技法は武術の本質そのものともいえる。今回紹介するものは、他敵を想定した”投げ放つ”技法群。
また、太刀・小太刀と得物が変化すれば攻撃法も変わり、さらなるバリエーションが生じてゆく。
「平成17年4月号」(3月14日発売)
第27回 対武器の技法 −合気杖における徒手技法「太刀取り」
日本伝大東流合気柔術に伝わる武器の技法群。
それは単に、武器の使い方に終始するものではなく、武器法即徒手技法に他ならない。かつて武士の表芸たる太刀に徒手にて対峙した時、その真意を悟るもので
ある。
「平成17年3月号」 (2月14日発売)
第26回 対武器の技法 −太刀を中心とした技法
今回は、太刀を中心とした捌きから、より実践的な間合いに進み、いよいよ徒手で武器に対峙してゆく。
「平成17年2月号」 (1月14日発売)
第25回 対武器の技法 杖・太刀・小太刀〜徒手の捌き
日本伝大東流合気柔術が前提としているものは、試合でなく実戦であり、故に当然、対武器である。今回より、合気柔術の別伝である合気丈、小太刀、懐剣術の
技法を中心に、妥協の許されない洗練された技法体系を紹介する。
日本伝大東流合気柔術 合気之階梯 シリーズ
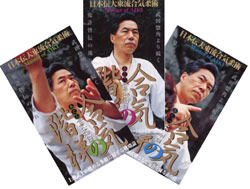 株式会社BABジャパンより、菅沢師範のビデオ・DVDが発
売されている。 株式会社BABジャパンより、菅沢師範のビデオ・DVDが発
売されている。
本シリーズでは、武田惣角から久琢磨、そして鶴山晃瑞へと続いた免許皆伝の流れを汲む菅沢恒元師範が、日本伝の合気の階梯を全三巻にわたって詳細に解説。
さらに恒元伝におけるもう一つの合気の階梯である「合気基本操法」も、一挙ここに公開されている。
合気を志す者、必見のシリーズである。
道場近況
出版記念の集い
 菅沢先生の「三大技法に学ぶ 日本伝大東流合
気柔術」シリーズの柔術編の出版を祝おうという事で、先日(平成18年2月11日)、菅沢先生をお招きしての廣瀬道場有志による、出版記念の集いが行われ
た。 菅沢先生の「三大技法に学ぶ 日本伝大東流合
気柔術」シリーズの柔術編の出版を祝おうという事で、先日(平成18年2月11日)、菅沢先生をお招きしての廣瀬道場有志による、出版記念の集いが行われ
た。
当日は廣瀬道場での稽古日という事もあり、また先生が蕎麦好きという事もありで、道場近くの蕎麦屋の二階を借りての集まりとなった。稽古の後で蕎麦を肴に
ビールなどという展開で、話の流れは日本伝から今の教育界にわたる所まで発展し、大変和やかな集まりだった。
廣瀬道場演武会
 平成17年12月24日、日本伝(大東流三
大技法)合気柔術廣瀬道場において、年末恒例の会員による演武会が行われた。 平成17年12月24日、日本伝(大東流三
大技法)合気柔術廣瀬道場において、年末恒例の会員による演武会が行われた。
今年も、日本伝ならではの特徴を生かした様々な技が披露された。
 切れ味鋭い技を繰り出す者、多人数取りに挑
戦する者、高度な固め技に取り組む者
と、それぞれの思い描く日本伝が展開された。 切れ味鋭い技を繰り出す者、多人数取りに挑
戦する者、高度な固め技に取り組む者
と、それぞれの思い描く日本伝が展開された。
 実は今回、菅沢師範からは、演武会に向けて
の稽古時間を与えていただく事がなかった。演武の受けを取る相手や、演武の構成も
直前に決まり、演武会は全くのぶっつけ本番となった。その結果、演武では各人の日本伝への習熟度が如実に現れた。 実は今回、菅沢師範からは、演武会に向けて
の稽古時間を与えていただく事がなかった。演武の受けを取る相手や、演武の構成も
直前に決まり、演武会は全くのぶっつけ本番となった。その結果、演武では各人の日本伝への習熟度が如実に現れた。
 私(このサイトの管理者)は以前、師範か
ら「本来の演武では技の打ち合わせなどはないものだ」と、伺った記憶がある。今回の演武会を通じて、自己の到
達度を計るという意味での演武というものを再認識させられた。 私(このサイトの管理者)は以前、師範か
ら「本来の演武では技の打ち合わせなどはないものだ」と、伺った記憶がある。今回の演武会を通じて、自己の到
達度を計るという意味での演武というものを再認識させられた。
演武会の最後は、菅沢師範による模範演武で締めくくられた。
 また、この日は年内最後の稽古日でもあった
ため、演武会の後は納会も開かれた。納会では、廣瀬道場主からお手製のケーキが振舞われるといった”クリスマス
プ
レ
ゼント”もあり、年末のひと時を楽しむ事が出来た。 また、この日は年内最後の稽古日でもあった
ため、演武会の後は納会も開かれた。納会では、廣瀬道場主からお手製のケーキが振舞われるといった”クリスマス
プ
レ
ゼント”もあり、年末のひと時を楽しむ事が出来た。
市民活動
”人に優しい「柔ら」の原理−やはらを現代に生かす−” 公開講座開催
平成16年10月2日、東京都小金井市成人大学講座において、菅沢師範による公開講座が行われた。当日は、”人に優しい「柔ら」の原理−やはらを現代に
生かす−”とのテーマで、4〜50人の参加者が日本伝大東流合気柔術を体験した。講座内容の概要は以下のとおり。
1.
「柔ら」の原理
1−1 柔ら(柔術)の特徴
1−2 日本伝合気柔術の特徴
1−3 合気柔術の基本原理(合気基本操法)
2.
「大東流女子武道」(昭和17年公開)の実技
参加者は、理論的な説明とともに菅沢師範が繰り出す日本伝大東流合気柔術の一端を目の当たりにし、その後、自らも日本伝を体験した。講座は大盛況のうちに
終了 となった。
過去の活動報告はこちら
|
 |
 |
|
|


